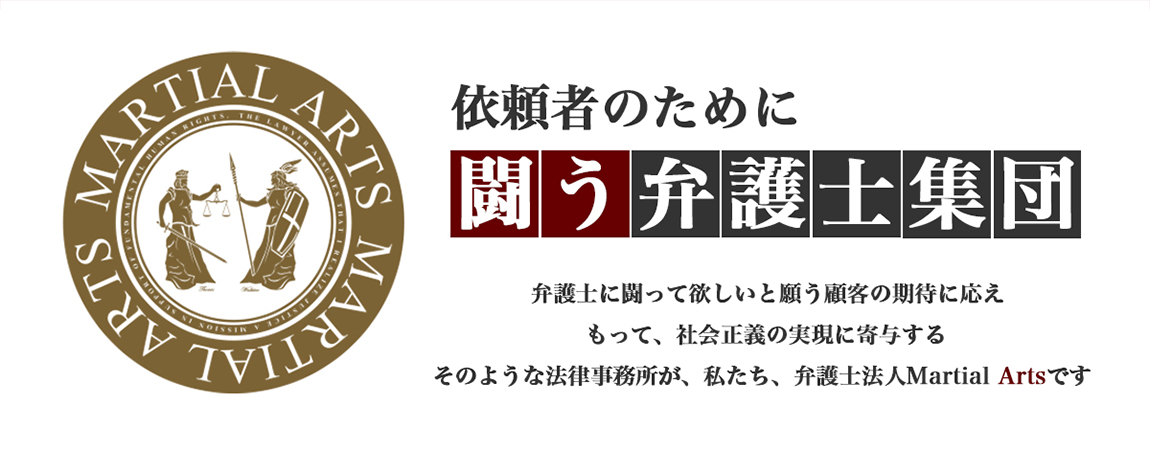
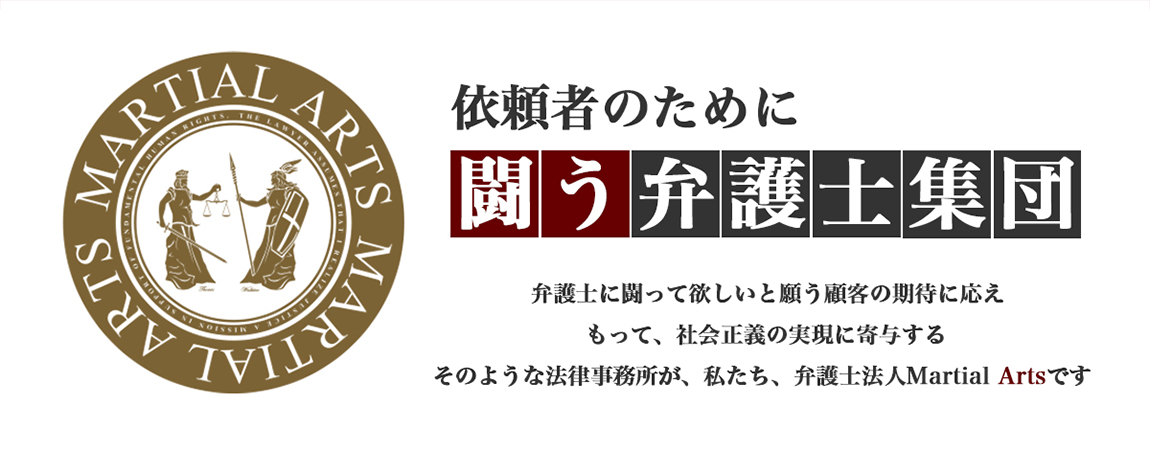
栗生悠佐弁護士が入所いたしました
【オンライン・会場】森川友和弁護士が2024年1月17日(水)に,一般社団法人企業研究会が主催するセミナーにおいて「新任担当者のための『ビジネス契約』作成の実務」と題する講演を行います
第77期司法修習予定者等の皆様へ~弁護士法人Martial Artsは2023年11月23日~11月27日開催≪東京三弁護士会 オンライン 就職合同説明会≫に参加いたします
【オンライン・会場】森川友和弁護士が2023年6月13日(火)に,一般社団法人企業研究会が主催するセミナーにおいて「新任担当者のための『ビジネス契約』作成の実務」と題する講演を行います
2023年1月1日付で宮川敦子弁護士がパートナーに就任いたしました
安易に和解を勧めて、闘いたいと思っている依頼者の気持ちに応えない弁護士、タフな交渉・攻撃的な準備書面を出してくる相手方弁護士に屈服し、依頼者の利益を守れない弁護士、裁判官から不当な和解を勧められ・あるいは常識はずれな判決を出された際に、そのままそれを受け入れる弁護士、このような弁護士は、顧客を裏切っていると言わざるを得ません。
弁護士法人Martial Artsの弁護士は、闘う弁護士として、お客様に以下をお約束します。
・闘う弁護士としての自覚を持っています。
・顧客のために闘う戦略を試行錯誤します。
・情熱を持って戦略を遂行します。
・戦闘力を高めるために日夜努力します。
・顧客のためになるのであれば、裁判所や相手方と衝突することを厭いません。
当事務所では、依頼者のために闘う弁護士がいるということを広く認知していただくため、法律相談料30分5,500円で応じております。まずは扉を開けて、気軽に悩みを我々にご相談ください。
法律相談料30分5,500円